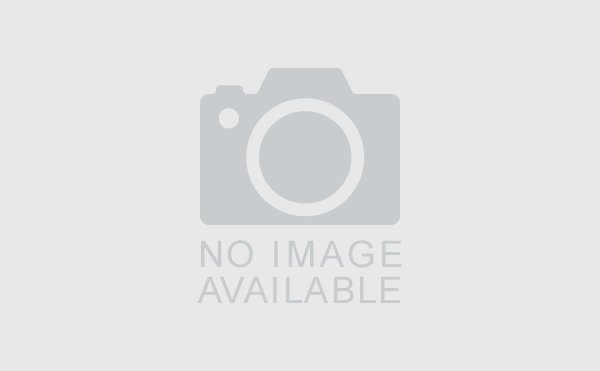矛盾が浮かび上がるとき
南極授業が授業であるために39
昭和基地周辺に点在する
この「迷子石」という素材を教材化するためには、
故郷富山の常願寺川に残る「大転石」が必要となった。
そこで、南極に行くまでにもう一度、
常願寺川の上流から下流まで歩いてみたくなった。
すると、
ある矛盾が浮かび上がってきた。
川幅が狭く
流速は速く
石は大きく
ごつごつしている。
川幅が広くなり
流量が増え
石はやや大きく
丸みをおびてくる。
川幅がさらに広がり
流量も深さも増し
石は細かく
丸い粒となる。
このように上流、中流、下流と、
その様子がどんどん変化していくのがよくわかる。
小学校理科では、
上流の石はごつごつしていて大きく、
下流(河口付近)の石は丸くて小さい、
と習う。
ある矛盾、というのはここだ。

昭和基地では、
その沿岸の波打ち際に(実際は凍っているので波打たないが)、
こんな大きな岩が
あちこちに見ることができるのだ。
小学校理科では、
下流(河口付近)の石は丸くて小さい、と習うのに、である。”