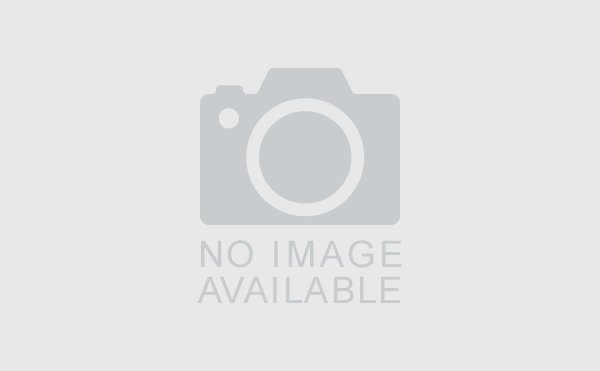比較物を練るのが授業者
南極授業が授業であるために38
迷子石は、
実に興味深い素材だ。
ただ、
それだけでは教材にならない。
迷子石の教材化のためには、
「もう一手間」が必要だ。
例えば、「比較の場」を意図的につくること。

この写真は、
昭和基地内最大の「迷子石」。
以前に紹介したPANSYアンテナ群の中で
まるで「迷子」なってしまったかのように
おそらく何十年、何百年もの間、ここでたたずんでいる。

この写真は、
故郷富山に実在する「大転石」。
暴れ川の異名をもつ常願寺川沿いに
ある日
突如として現れて以来、
今も自然の猛威を
私たちに無言で語りかけている。
この両者を比べるてみると
子どもの心は動き出す。
富山と南極はこんなに離れているのに、
なぜ、同じような石があるのだろうか、と。
異なるものなのに、共通性を見いだそうとするのだ。
また、比べてみることで
子どもの心はその反対に動くこともある。
富山の大転石は常願寺川の災害で「置き去り」にされたはずなのに、
昭和基地の「迷子石」の近くには、そんな大きな河川はないよ、と。
同じようなもののの中に、異質性を見いだそうとするのだ。
ただ、この比較物は何でもよいわけではない。
子どもを揺り動かす比較物の力を知るがゆえに
その比較物を何にするか腐心するのが
授業者。
その比較物が特になくても
何とかしてしまえるのが、
説明者?解説者?”