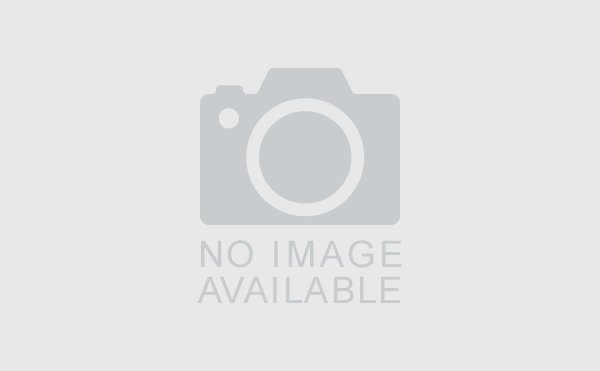3つの偶然
南極授業が授業であるために16
この「素材」が「教材」になったのは
まさに偶然に偶然が重なってのことだった。
まず、1つ目の偶然は、
その「アザラシのミイラの発見」だった。

この日は、しらせで同室だったH隊員を含め数名で行動していた。
そのH隊員がふとつぶやいた。
「あれえ、これ、なんですかねえ。。。」
それはとても落ち着いた口調だったので、
それが、ほぼ完璧な状態のミイラだと認識するまでには、
少し時間がかかった。
2つ目の偶然は、
そのアザラシのミイラが、
眠るように真上を向いて横たわっていたことだ。
その背後には、
何千年、何万年もの間に積み重なった氷河の壁がそびえている。
私たちがいるこの空間だけ
まるで時間が止まっているようだった。
3つ目の偶然は、
日本を発つ前に、
ある博物館で開催されていたツタンカーメン展を
私は訪れていたことだった。
そのせいだろうか。
何千年、何万年と積もった氷河の前で、
眠るように横たわるその様は
まるでツタンカーメンの棺のように
私には見えたてきたのである。
そう思ったとたん、
「アザラシのミイラ」から、
何やら得体の知れない荘厳さが伝わってきたのである。
この瞬間、
これは「教材」へと昇華した。
私は、自然解説員ナチュラリストではない。
また、ミニ研究者やミニ博士でもない。
一介の教員として、
自分の目で見て、
自分なりに感じたことを、
自分の言葉で、
子供たちと向き合わなければならない。
ここ南極ではずっとそう思ってきた。”