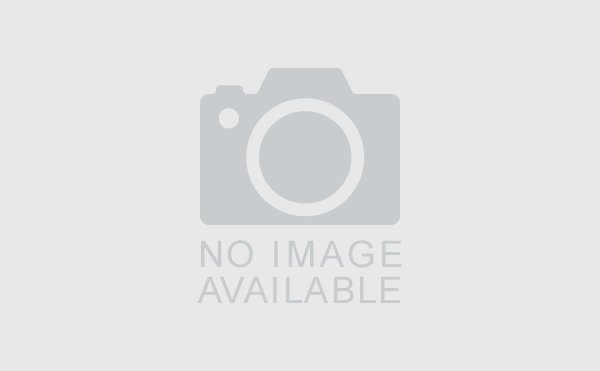問いが生まれる
南極授業が授業であるために11
われわれ同行教員が「南極授業」で本質とすべきことは、
むしろ、
「学ぶことや生きることの意味」のようなものではないだろうか。
「1000本もあるのに、1本1本手作業で立てていく姿」や
「過酷な状況下であるのに、目的を達成するためには努力を惜しまない姿」そのものが
授業の教材となるのである。
子ども達がその教材に直面した時、
「なぜ、そうまでしてするのか」
「人を突き動かすものは一体何なのか」
という問いが生まれる。
問いが生まれれば、そこに
子どもは類推を働かせ、
やがて思考を組み替え、
新たな推論を展開し、
これまでになかった概念を一人一人の中に形成していく。
そういうことは、
子どもの主体的な学びを大切にしてきた
先輩教員たちの日々の授業研究の中で
すでに明らかになってきていること。
だから、その流れを受け継ぐ一人の授業者としては、
たとえ「南極授業」が
限りなく一方通行に近い状況下で行うものであっても、
そこに少しでも主体的な学びが成立するよう、
ぎりぎりまであきらめないで
挑戦し続けなければならなかったのである。
そうして出来上がったこのコンテンツは、
今も時々、
子ども達とのミニ南極授業に登場するのだが、
比較的好評である。
そういう子ども達の姿を見るにつけ、
先輩教員に実践によって明らかにされてきた授業の本質は、
今も昔も変わらないのだと痛感させられるのである。
授業は、
その本質をとらえてさえいれば、
子ども達を引きつけて離さない。”